目が悪くなる前は、毎日本を読んでいました。
病気で中心視野が欠けるなどして本が読めなくなった時は、本当に悲しかったです。
でもその後、他の手段で読書を取り戻すことが出来ました。
ここでは本を読むための色々な方法を挙げてみます。
通常の本や新聞を使う方法
まずは、老眼や視力の障害が軽い人向きの方法です。
+1.00くらいの老眼鏡を重ねつけてみる(老眼)
いつも読書をする時のメガネを掛けて、百均などの低い度数の老眼鏡を重ね付けしてみてください。
はっきり言ってとっても変ですが、
- 度数が上がること
- 重ね付けの老眼鏡のレンズが、目との距離が少し開くこと
などにより、本の中の文字が少し大きく見えると思います。
(プラス度数のレンズを目から離して使うと、なんちゃってルーペみたいになります)
私の場合は有効だったのですが、他の人の場合どうかわからないので、百均の老眼鏡売り場で軽く試してみてはどうかと思います。(自己責任でお願いします)
視野の広いルーペを使う(新聞)
ただでさえ大きな誌面で、改行だらけの新聞。
ある程度の視力がある人には、倍率低めの広視野ルーペが適しているでしょう。
例えば下画像はエッシェンバッハのルーペですが、倍率2.0倍、レンズ系は12cmという視野の広さ。
新聞や広告など、広い誌面をあちこち移動して見る場合に適しています。

楽天で見る
装着型のルーペを着けて読む(本)
装着タイプには、メガネルーペ、ヘッドルーペ、ネックルーペなどがあります。
また、手持ちのメガネにクリップなどで装着するタイプもあります。
メガネルーペとヘッドルーペは目の近くにルーペがありますが、ネックルーペはもう少し離れた位置にレンズが固定されるので、それぞれ使い勝手や向き不向きに差があります。
メガネ・ヘッドルーペは視界全体が拡大されることになるので、酔いを感じる場合もあると思います(私はそうでした)。
低倍率で済む人がピンポイントの時間で使うのが適しているのではないかと、経験からは思います。
また、メガネタイプで男女兼用のものは、女性には大きくてずり下がってくる可能性があります。
そうすると不快で不便でわずらわしくて仕方ないので、購入時にはその点も考慮します。
メガネタイプの一例(エッシェンバッハ)
デスクルーペ、バールーペを使う(新聞)
見たい対象物の上に直接置いて使うタイプのルーペがあります。
利点はピント調整が簡単になること、ピントのずれによる目の疲労や不快さが少ないこと、見たい場所を見失いにくいこと、ルーペを持った手をずっと持ち上げたままでいる必要がないことなどです。
デスクルーペはドーム型や短い筒型の形が多く、バールーペはその名の通り「バー」状で細長いため、行を追うのに適しています。
デスクルーペの例
バールーペの例

書見台
こちらはルーペやメガネではなく「台」ですが…
机などに置いた書類を、ルーペなどで長時間覗き込む姿勢って疲れます。
書見台を併用して高さや角度を変えることで、見るのを楽にできる可能性があります。
目から近い方が見やすい場合は、脚付きの書見台の方が良いかもしれません。
書見台の例
電子書籍で読む(本)
例えば文庫本のように文章がメインの本は、電子書籍ならば文字の大きさやフォントの種類、背景色と文字の色などを選ぶことができます。
電子書籍は、AmazonのKindle、アップルのiBooks、楽天のKobo、BookLive、honto、 ebookjapan(漫画)など、いろいろあります
それぞれ読むための専用のアプリが必要ですが、アプリ自体は無料です。
文字をどのくらい拡大できるのか、どういう配色を選べるかなどは、アプリによって異なります。
実用書や雑誌のように写真やイラストが多いものは、ページをそのまま画像ファイルのように取り込んだ感じ(=レイアウトが固定されている)なので、目が悪いと見えにくいです。(ページの写真を撮って(スキャンして)、それを拡大して見るような感じ)。
ちなみにKindleもiBooksも、VoiceOver機能を使って音声読み上げさせることも可能です。
私はサピエ(下記)にない本などは、Kindleで電子書籍を購入し、VoiceOverで音声読み上げさせて聞くことが多いです。
これら電子書籍について詳しくは、別のページで紹介したいと思います。
オーディオブック(音声図書)で聞く(本)
audiobook.jp(前FeBe)や、Audible(オーディブル)など、オーディオブック(音読された本を、耳で聴くもの)を利用するという手もあります。
Appleのオーディオブックストアも、ラインナップが少なそうですが、あります。
また、視覚障害者認定を受けている人は、サピエに登録(障害者手帳などが必要)して、録音図書を聴くことも出来ます。私の読書の9割以上はサピエです。
サピエについては別のページで詳しく書きます。
オーディオブックは大抵無料お試し期間が設けられているので、それを利用するのが良いと思います。
個人的にはオーディブルは読み手の演技と自己主張がうるさく感じてうんざりし、合いませんでした。
好みの問題ですが、Kindle本を購入して音声読み上げしてもらう方が遥かに快適です。
音声読み上げ機能で聴く
Apple製品のことしか知らないのですが、おそらくアンドロイドなどでもあるのではないでしょうか。
AppleのVoiceOver機能を使って、電子図書を音声読み上げさせることができます。
私の場合は、サピエに目的の本がなくKindleにあった場合は、電子図書を購入して、VoiceOverで読み上げてもらって聞いています。
他のページで、実際のやり方を紹介したいと思います。
アプリでカメラ撮影して読み上げ
スマホのアプリで、カメラに映った文字を読み上げてくれる便利なアプリがあります。
あのマイクロソフト社が作った「Seeing AI」というアプリは、本当に色々すごいです。
他のページで書いているので、併せてご覧ください。
番外編1:PDFに変換
かつて私は、本のページを1枚ずつ破り、1枚ずつスキャナでスキャンして、章ごとにPDF形式で保存、パソコンで拡大して見る…という恐ろしく手間暇のかかることをしていました。
見る必要があったし、でも本の文字は小さくて見えないし、どうしようもなかったのです。
著作権で問題になった自炊代行サービスがありましたが、難しいことは分かりませんが、裁判で 敗訴したとのこと。
うんと拡大すればどうにか見えた者の一人として、厳しい利用基準を設けてくれて良いから、こういうサービスは存在して欲しかったです。
それが無理なら全書籍の電子書籍を作って欲しい。
知的欲求を満たせず諦めざるを得ないというのは、辛いものです。
番外編2:青空文庫・青空朗読
青空文庫は、著作権切れの本や著者が承諾してくれた本を、ボランティアの方々がテキスト化して、ネットにアップしてくれたものです。
テキスト化されているので、読み上げ機能を使って読み上げさせることも出来ます。
また、青空文庫の朗読を聞くことが出来る「青空朗読」もあります。
どちらもインターネット環境さえあれば、誰もが本を読み、聞くことができるサービス。
本当にありがたいことです。
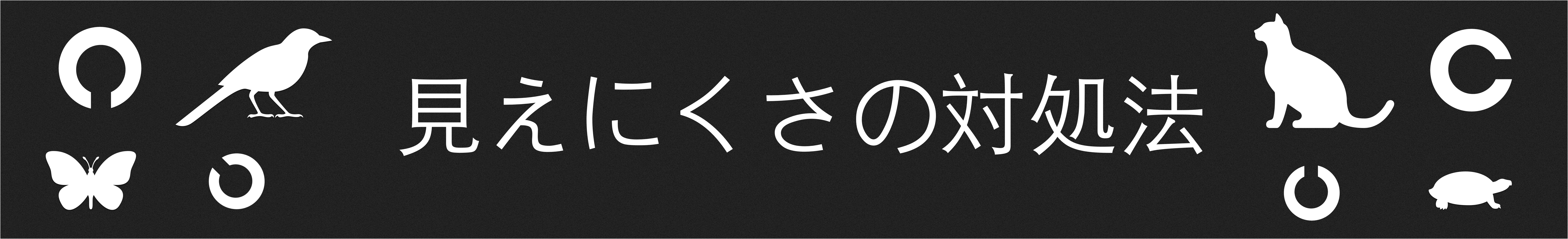


コメント